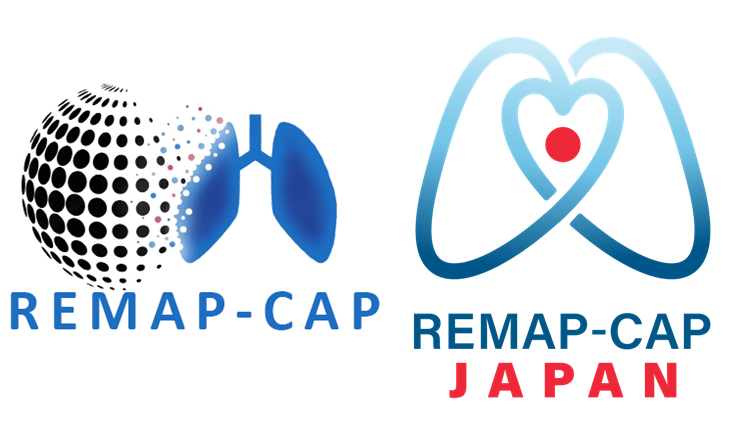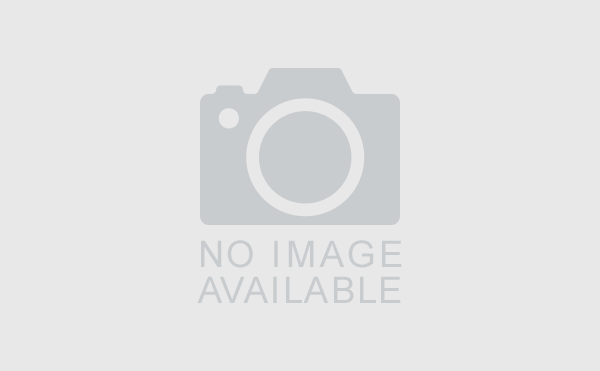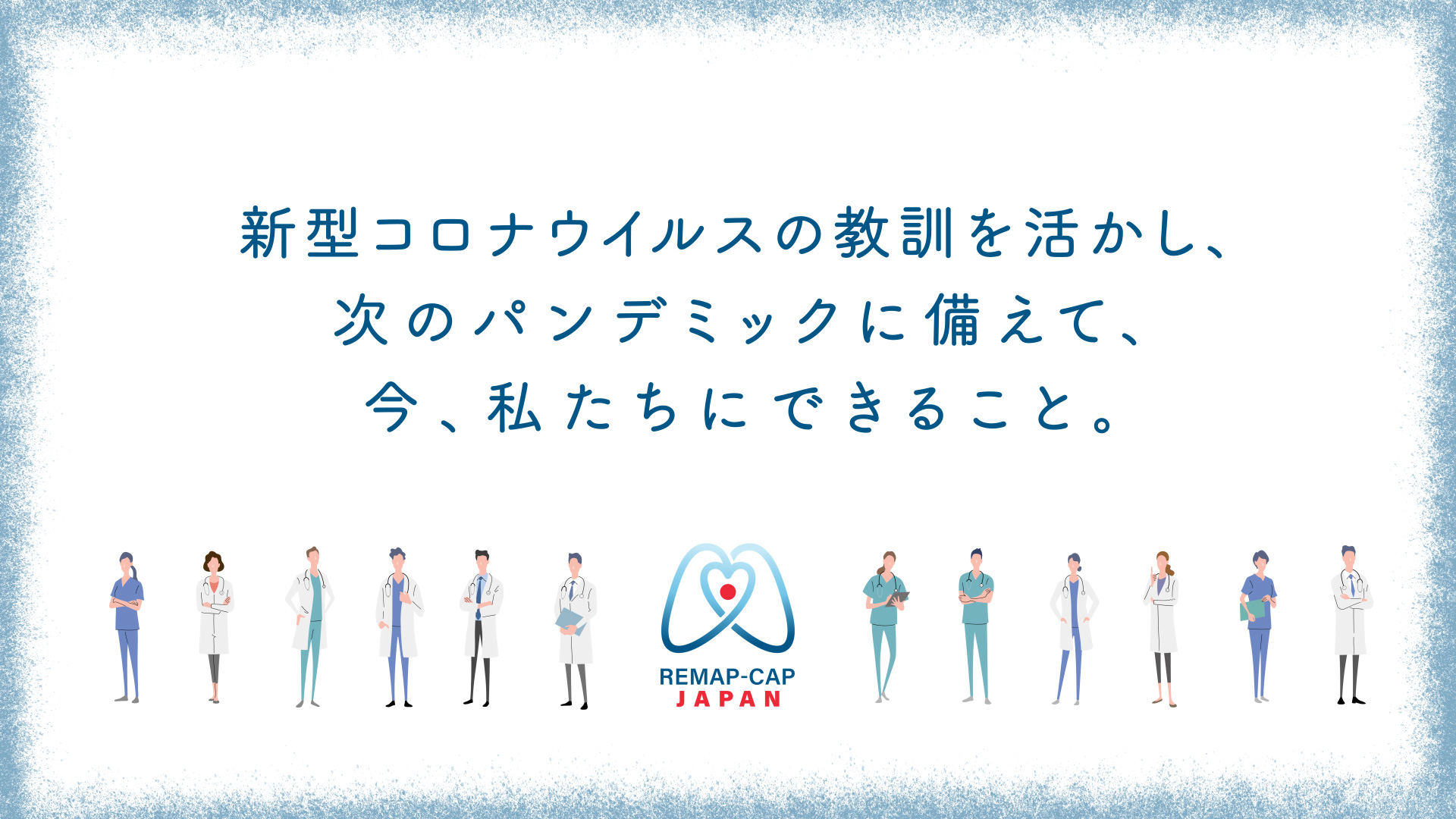抗凝固薬ドメインですが、治療量armでは未分画ヘパリンを用いてAPTT 1.5-2.5とする介入になるのだと思いますが、低用量armと中等量armでは国内の保険適応の範囲において具体的にどのような選択肢があるのでしょうか?また、それらの選択肢のうちからどの介入を用いるかを前もって選んでおく必要はありますか?
未分画ヘパリンの治療量でのAPTT目標はphysician discretion、つまり施設や医師レベルで設定していただいて構いません。ここでいうところの低用量は通常の予防量の事と理解していますが、そちらはドメインの最後に各用量が記載しておりますように、一般的な体重ではヘパリンCa 5000単位皮下注12時間おきですので、日本での通常診療とあまり乖離はないと考えています。中等量は一般的にヘパリンCa7500単位皮下注12時間おきとなりますが、こちらも保険適応範囲内で問題ないと事務局としては考えています。基本的には、本ドメインはデフォルトでは通常の予防量もしくは中等量の2つの介入からのランダム化割付としてデザインされていますが(ですので、どちらかのみに参加するというよりは基本的には)、未分画ヘパリン静注の継続という介入は、ランダム化以前に同一登録患者が未分画ヘパリン静注を受けている場合のみ割り付けられる介入として残るため、その場合は基本的には3つの介入からランダムに割り付けられることになります。後者の場合は、厳密には未分画ヘパリン静注の継続 vs 通常の予防量、もしくは、未分画ヘパリン静注の継続 vs 中等量、という2つのみのランダム化割付にしてほしいと施設レベルでリクエストは可能にはなりますが、現実的にはそのようにリクエストする意義は乏しいかと思われます。